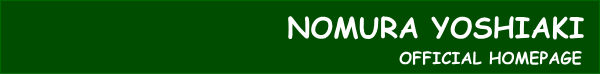日本における通説である管轄配分説は、民訴法の土地管轄の裁判籍を、国際的配慮を 加えて柔軟に解釈することに道をひらいた。さらに、最高裁判例によって認められた 「特段の事情理論」は、具体的事情に関する総合的判断によって、裁判管轄の判断が 左右されうること示している。また、離婚の裁判管轄に関する最高裁平成八年六月二 四日判決民集五〇巻七号一四五一頁が、「当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期す るという理念により条理に従って決定する」との一般原則を採用したことにより、当 事者と法廷地との関連を条理に照らして判断するという枠組みは、条理説へのリップ サービスではなく、国際裁判管轄の一般理論となったといえる。
また、次の判例は、日本と事件との関連性が日本の国際裁判管轄の一般的基礎である ことを説示している。まず最高裁平成九年一一月一一日判決(預託金請求事件)民集 五一巻一〇号四〇五五頁は、「被告が我が国に住所を有しない場合であっても、我が 国と法的関連を有する事件について我が国の国際裁判管轄を肯定すべき場合のあるこ と」を認めた。次に最高裁平成一三年六月八日判決(著作権確認等請求事件・ウルトラマン事件)民集五五巻四号七二七頁は、被告 が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関 係のような「・・事実関係が存在するなら、通常、被告を本案につき応訴させること に合理的な理由があり、国際社会における裁判機能の分配の点からみても、我が国の 裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということができる・・・」と判 示した。さらに前掲離婚判決は、被告の住所は国際裁判管轄の決定にとって重要な要 素だが、「被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素 から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合」があ るとした。
このような日本の学説・判例の傾向は、他に特別の定めがない限り、土地管轄規定が 国際裁判管轄規則の機能をも果たすとするドイツ的二重機能説とは異なる。また、前 述した日本の民訴法学の有力説である逆推知説とも違う。むしろ、州のロング・アー ム法上の管轄原因が存在しても、連邦憲法のデュー・プロセス条項によって州の裁判 権行使を制限する米国の仕組みに近いといえる。また、国家法によって定められた裁 判権行使の範囲を、特段の事情の判断を通じた裁判所の「解釈」によって縮減するこ とを認めるのは、管轄法理に米国法におけるフォ-ラム・ノン・コンヴィニエンスの 法理と同様の柔軟性をもたらしている。もっとも日本の特段の事情理論は、特段の事 情が認められれば日本の国際裁判管轄を否定するというかたちをとるが、米国のフォ -ラム・ノン・コンヴィニエンスの法理は、裁判権行使が適法なことを前提として、 これを差し控えるのである。
以上のような日本における最近の学説・判例の傾向を前提とする限り、日米の管轄 法理はかなり類似している。とりわけ、民訴法上の①裁判籍の判断プラス②特段の事 情の判断による日本の最高裁判例は、合衆国最高裁の①最小限の関連プラス②合理性 (フェアネス)テスト(二段階テスト)ときわめて近い。筆者自身は、日本の裁判管 轄法理の解釈に無批判に外国法の理論を持ち込むことには批判的である。しかし、一 国の裁判権行使の範囲を、最小限の関連プラス合理性(フェアネス)テストで判断す る米国型の枠組みは、国際裁判管轄の問題を訴訟要件や特段の事情のレベルで考える のか、憲法上の基本権として考えるべきか、日本の裁判管轄規則の一般条項を考える 上で重要な示唆を与えてくれるであろう。また、このことは、ノボ・インダストリー 事件に見られたように、日本における独禁法事件において日本に住所や営業所を有さ ない被審人の手続権をどのような制度で保護するかにも関係する問題である。 |