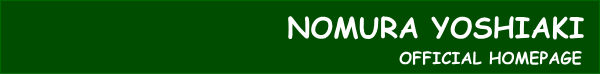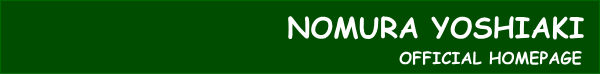|
本判決は、第二に、Y2社の法人格を否認してX社・Y2社間の契約上の責任を山一證券に帰属させるべきかどうかという問題を、山一證券の債務不履行責任の問題ととらえ、その準拠法をX社・Y2社間の契約準拠法とし、X社・Y2社間に準拠法を日本法とする黙示の合意を推認して、これを日本法と解した。法人格否認の目的を事案との関係で実質的に理解し、問題となる契約の準拠法によったところは、②の先例同様(フランス法を準拠法とした点を除き)、学説の大勢に従ったものと評価できる。契約準拠法の決定方法について、法例七条一項の当事者の意思には黙示の意思が含まれると解されているが(最判昭53・4・20民集三十二巻三号六一六頁、最判平9・9・4民集五一巻八号五七頁)、本判決は法例の条文には言及していない。Y1も、当事者間ではバハマ法を準拠法とする黙示の合意があったというのみである。これに対して、X社は法例七条二項により準拠法は行為地方たる日本法であると主張していた。国際私法においては、明文の規定がない場合には条理によって準拠法を決定するときがある(最判平14・9・26民集五六巻七号一五五一頁、特許権侵害の差止請求の準拠法)ので、明文規定があるときにはこれを明示すべきである。他方、民法上の一般条項に基づいて法人格否認の法理に私人間の契約の効力を左右するような機能を認める場合には、法人格否認の法理は強行法規そのものであり、準拠法のいかんを問わず適用が求められる場合もあることを認めるべきである。本判決の立場では、本件債券現先契約の準拠法が外国法であった場合には、先例②のような立場をとらない限り、法人格否認の法理は適用されない。日本の法政策として、本件のような事案において子会社の契約責任を親会社に帰属させることが強く要請されるとすれば、むしろ法人格否認の法理を契約準拠法のいかんに関わらず適用されるべき法任地の強行法規としてその適用を説明すべきであろう。
|